


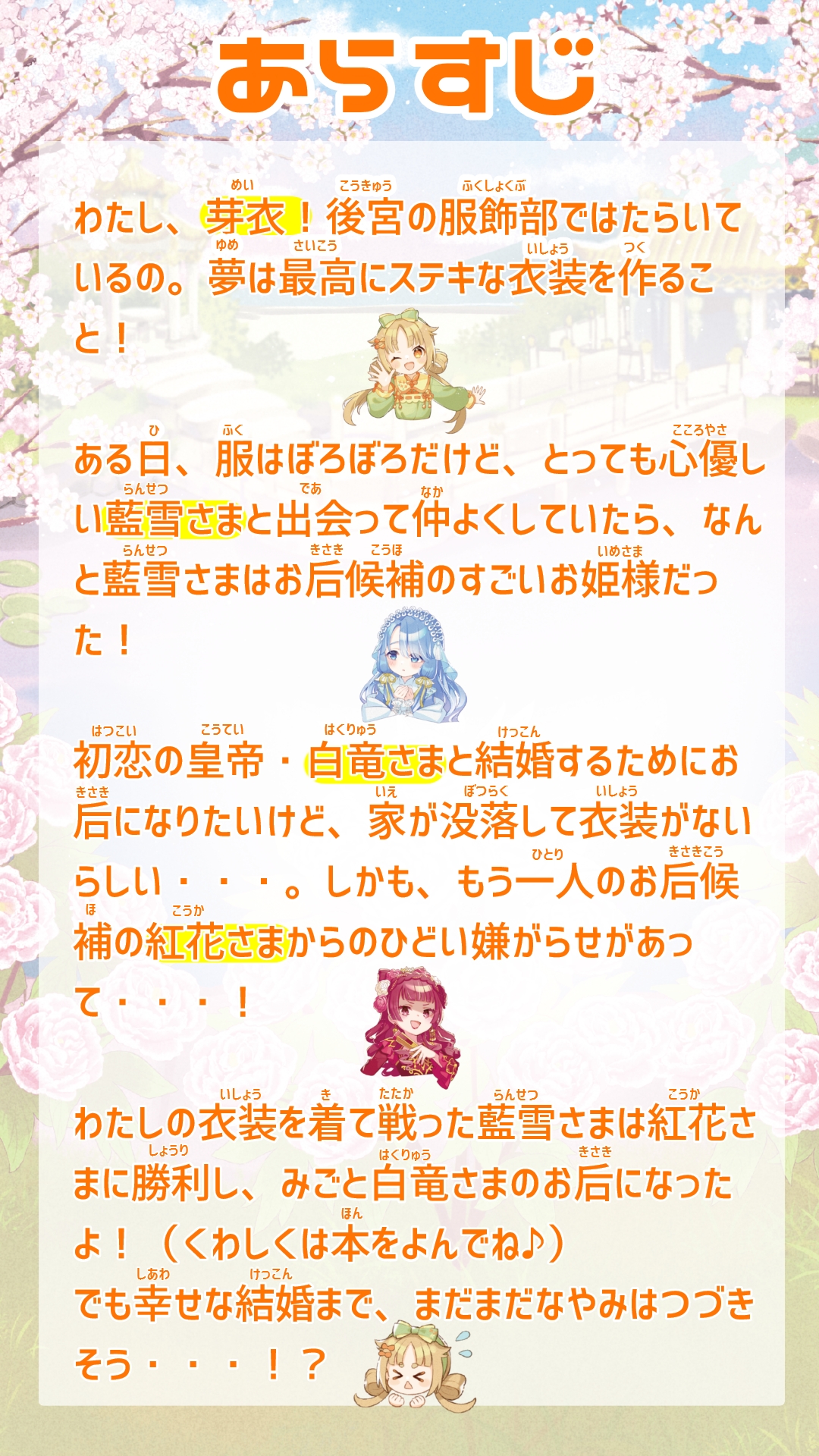


第9章
わたしたちは宮廷につくと、役人に花瓶を渡した。これで仕事は終了。あとは当日、役人たちが会場に花瓶を飾ってくれるはずだ。
それで、わたしたちが帰りましょうか、って話をしているときだった。
「紅花。宮廷で会うのはめずらしいな」
「お父さま!」
声をかけてきたのは、いつか白竜さまの執務室で見た男の人だった。
紅花さまのお父さん――大臣だ。
やっぱり、ふたりって似てるなあ。豪華な衣装ってことも、同じだよ。
ふたりあわせて、衣装代はいくらになるんだろう……。
「今日は紅花にいい報せがあるぞ」
大臣が上機嫌に笑うと、紅花さまは首をかしげた。そんな紅花さまになにか言おうとした大臣だけど、「む」とわたしを見る。
「さがりなさい。娘と話がある」
うっ、じゃま者めって空気をばしばし感じるよ!
わたしは「失礼します!」って、そそくさとその場から退散した。
ふたりで話ってなんだろう。「今日の晩ごはんはこんがり焼いた、お高いお肉だぞ~!」とか? ……いや、庶民的な会話すぎるか。言ってたらおもしろいけど。そもそもふたり、べつべつに暮らしてるし。
馬車で待っていると、しばらくして紅花さまたちがやってきた。
「――ということだ。『百命花の舞』、期待しているぞ、紅花」
聞くことができたのは、それだけだった。舞をがんばって、って話かな?
でも紅花さまは、なんだか浮かない顔をしてる。その表情のまま「がんばります」って大臣と別れて、馬車に乗りこんできた。
「紅花さま? なんのお話だったんですか?」
「なんでもないわ。――ねえ、あなた、簡単に舞手をやめないわよね?」
「え? それはもちろん、やめませんけど」
紅花さまは、すこし不安そうな顔でわたしを見ていた。
どういうこと? 本当になんの話をしていたんだろう……?
その翌日のことだ。
毎日の練習でさすがにみんな疲れていたから、今日の練習は休みってことになった。
それで天陽宮でのんびりしていたら、藍雪さまの声がした。
「芽衣、今日はいっしょに宮廷へ行かない?」
「宮廷に? お仕事ですか?」
「いいえ、白竜さまにお茶菓子を持っていこうと思って。ほら、白竜さま、最近はお疲れのご様子だから」
ああ、そういえばそうだったね。いつもきらきらな白竜さまが、最近は顔色も悪くて、元気がないんだった。
「おいしいお菓子とお茶で、休んでもらいたいの」
心配そうな藍雪さまは、本当に白竜さまのことが大好きなんだって伝わってくる。
うん、それなら当然、おともするよ!
「お茶はあれですか? 雪殿名物、野草のお茶!」
「ふふ、白竜さまにあのお茶はさすがに出せないわ。買ってきた茶葉よ」
「えー、わたし、野草のお茶大好きですけどね。白竜さまなら、にこにこで飲んでくれそうな気がします」
「それはたしかに……。でも、相手は王さまだから」
くすくすと笑いながら、ふたりで馬車に乗って宮廷へ。
ゆっくり藍雪さまとお話するのは久しぶりだから、楽しい!
楽しすぎて、宮廷にはあっという間についちゃった。
でも、執務室には、やっぱり元気のない白竜さまがいて心配になる。
それに、わたしたちを見た白竜さまは目を見開いて、視線をそらした。あれ?
「白竜さま?」
藍雪さまも戸惑いがちに声をかけると、白竜さまはぎこちなく笑った。
「なんでもないよ。お茶会だね、ありがとう。あ、近くに雷斗もいるはずだから、呼びにいこうか。仲間はずれにしたら、すねるだろうから」
雷斗さまに会えるのはうれしいけど……、白竜さま、本当に大丈夫かな。
わたしと藍雪さまは顔を見合わせた、そのときだ。
「白竜さま、昨日のご英断にお礼を申しあげたく参りました。いやあ、よいお答えが聞けてよかった! ……おや」
扉が開いて、大臣が入ってきた。昨日ぶりだ。大臣もそう思ったのか、わたしを見て、片方の眉をあげた。でもすぐ、ご機嫌な顔になる。
「やはり側室はいるべきですからね。うちの娘ならばふさわしいですし――」
「……大臣!」
ぴしゃりと、白竜さまの声がした。
「ここで、その話をしないでくれるかな」
び、びっくりした。ど、どうしたの、白竜さま……。なんか、ぴりぴりしてる?
「――側室?」
そんな空気の中でつぶやいたのは、大きく目を見開いた藍雪さまだ。
え、藍雪さまもどうしちゃったの……?
白竜さまはなんて言ったらいいのかわからないような、複雑な顔をした。
代わりに、大臣が笑う。
「そうですよ。『百命花の舞』を成功させた姫に、ほうびとして側室の座を与えると、白竜さまが約束してくださったのです。だから」
「ごめんね、藍雪。お茶会はまた今度。今日はもう後宮に帰って」
大臣の言葉をさえぎって、白竜さまが言う。その強い語調に、わたしたちは白竜さまに言われるがまま、部屋を出るしかない。
でも、なんなの、この展開。
さっきまで、楽しいお茶会になりそうってわくわくしていたのに、意味わかんない。
なんでこんなに、空気が重いの……?
「藍雪さま、あの、いったいなにがどうなってるんですか?」
藍雪さまは不安そうに胸の前で手を組んだ。
「大臣は……、白竜さまが側室をむかえる、と言っていたわね」
すっと、藍雪さまが息を吸う。
「――側室は、王の結婚相手みたいなものよ。后以外の」
え……? 王さまの結婚相手? しかも、后以外の?
「な……、えっ? なんですか、それっ!」
「王族の血を絶やさないために、結婚相手は多い方がいいだろうって考える国もあるみたい。この国も、むかしはそうだったみたいよ」
「后がいるのに、ほかのひととも結婚しちゃうんですか?」
「国や時代によって、いろいろな考え方があるの。最近この国では、后ひとりを大切にする王さまがつづいていたから、側室はいなかったのだけれど……」
そう言った藍雪さまの声がふるえていた。
藍雪さまが言うには「后より立場が低いけど、王さまに嫁いだお姫さま」のことを、側室って呼ぶらしい。
大臣はその側室を白竜さまがむかえる決意をした、って言っていたんだ。
……って、んんんっ⁉ ちょっと待ってよ!
「ど、どういうことですか! 側室ができちゃったんですか⁉」
「わからないわ。……いえ、どうしてこうなったのかは、わかるのだけど」
藍雪さまはうつむいて、泣きそうな声でつづける。
「后ほどではないけれど、娘を側室にできればその家は栄えるわ。だから、大臣が白竜さまに『側室をつくれ』と言ったんでしょうね」
そんな――、藍雪さまと白竜さまは新婚さんなんだよ。いきなり側室なんて。
というか、白竜さまはそれを受けいれちゃったの……⁉
「藍雪どの! 芽衣!」
ぱたぱたとかけてくる音がした。息を切らして走ってきたのは、雷斗さまだ。
「側室の話、聞いたんだって……? 動ようしてると思うけど、聞いてくれ。兄上もこんなの望んでないんだ」
雷斗さまがくやしそうにこぶしをにぎった。
「藍雪どのが后になってから、兄上はずっと貴族たちに圧力をかけられていて――」
「圧力……?」
「貴族たちはみんな、自分の娘を側室にしたいと望んでる。側室は后とちがって、人数に制限がないからな」
白竜さまが断っても、みんなしつこく「側室を」って願っていたらしい。
だけど、断りつづけるのも限界がある。
「兄上が貴族をこばんでいると、その貴族全員が兄上の敵に回るかもしれない。そうなったら兄上は困るし、政務がとどこおって民も困るだろう」
「それは……、わかりますけど」
「兄上は若いから、貴族たちになめられてるんだ。后選びは王に権限があったからよかったんだが。側室選びは貴族の口出しができるものだから、みんなうるさくて」
白竜さまは、そのせいでこばみきれなかったってこと……?
雷斗さまが目を伏せた。
「兄上も悩んでいたし、どうしようもなかったんだよ。でもいまもずっと、兄上は藍雪どのを大切に考えている。それは間違いないんだ」
「白竜さまがお疲れのご様子だったのは、このためだったということですか。じゃあ、側室の話は本当なのね……」
藍雪さまがつぶやくその声が、いまにも泣きだしそうで、胸が苦しくなった。
状況はわかったけど、でも、こんなのってないよ……!
「悪い、兄上と大臣をふたりにはしたくないから、俺はいくよ。でも兄上を悪く思わないでやってほしい。頼む」
雷斗さまは心配そうにしながら、走っていった。
わたしたちは馬車にもどったけど、空気はしんとしている。
(藍雪さまになにか言いたい。でも、なんて言えばいいんだろう)
好きな人に、自分以外の結婚相手がいるなんて、嫌に決まってるよね。
本当に、どうしてこんなことになっちゃったの……!
「――芽衣」
「あ、藍雪さま⁉ 大丈夫ですか?」
藍雪さまの瞳から、涙がこぼれてる。ど、どうしよう!
「――あのね、芽衣。大臣はこう言っていたでしょう。白竜さまが、『百命花の舞』を成功させた姫に、ほうびとして側室の座を与えることを決めたって」
「はい、たしかそう言っていました」
「紅花が側室になると、まだ決まったわけじゃない、ってことよね……?」
あ! そっか! たしかにそうだ!
「そうですよ! まだ、なんとかなるかもしれません!」
「ええ、紅花が舞を成功させなければ、側室にはならない。……だったら、芽衣」
藍雪さまが、きゅっとわたしのそでをつまんだ。
ぽろぽろ泣きながら、わたしを見つめる。迷うように目線をさまよわせて、言った。
「お願い。舞手を辞退してちょうだい」
……え?
「紅花なら、舞台に出てしまえば、確実に舞を成功させるわ。そうなったら、わたしは――。だからお願いよ。あなたが舞手を辞退すれば、紅花は儀式に出られないから、側室の話はなくなると思うの」
「藍雪さま……」
それは、そのとおりだ。……だけど。
「そうなったら、『百命花の舞』は失敗しちゃいます」
ぴくっと藍雪さまの肩がゆれた。わたしも苦しい。でも、でもね。
「藍雪さまと白竜さまが成功させたいって思って、みんなが楽しみにしていた儀式が、失敗しちゃうんです」
「……そうね」
「紅花さまは、きっとすごく困ると思うし、くやしいと思います」
今回、どれだけ紅花さまががんばっていたのか、わたしは知ってる。
そのじゃまを、わたしはできないよ……。
それになにより。
「藍雪さまは、それでいいんですか……?」
やさしい藍雪さまは、紅花さまを困らせて後悔しない?
藍雪さまはきゅっと表情をゆがめた。それから、手で顔をおおう。
「わかってるの。紅花をいじめたいわけじゃない。后として、彼女を応援して儀式を成功させたいって思う。芽衣がたくさん練習した舞を、わたしも見たい。だけどね、芽衣」
涙にぬれた、藍雪さまの声がする。
「わたしは、白竜さまが大好きなのよ……!」
藍雪さまの声が、胸をつきさしてくる。
……わたし、なにも言えないよ。
そういえば、昨日「簡単に舞手をやめないか」って、紅花さまが聞いてきたんだった。
きっと紅花さまも、大臣に側室の話を知らされたんだ。
紅花さまは、いま、なにを考えているんだろう。

