


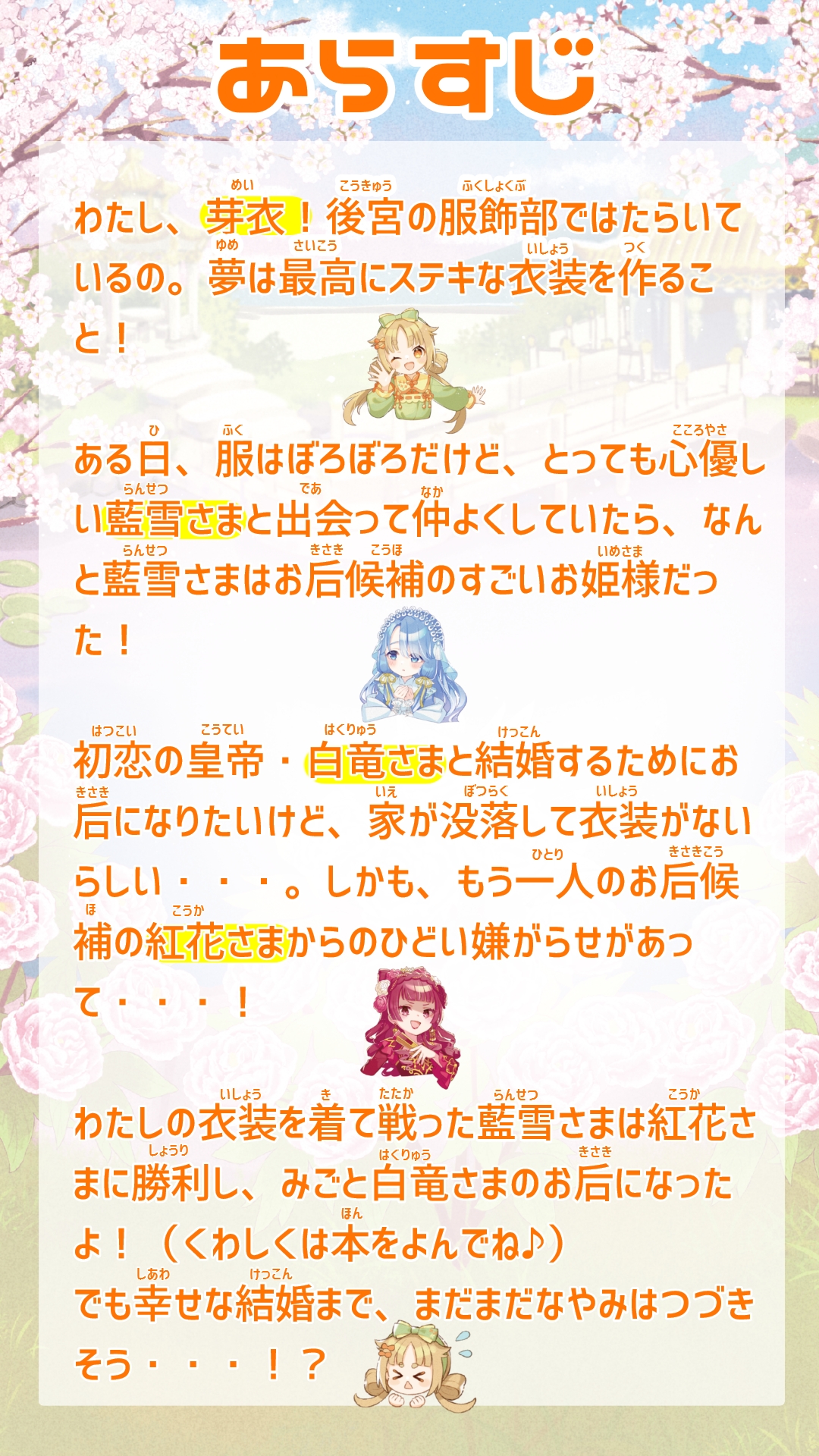


第●章
「芽衣、本当に大丈夫? やっぱり、護衛をつけたら?」
眉を下げた藍雪さまが、わたしの手をきゅっとにぎってくる。
この前、帰り道で襲われてから、藍雪さまはずっと心配してくれてるんだ。
そのたびに、わたしはじーんと胸が熱くなる。
でも、毎日護衛を頼むのは申し訳ないし。
「人通りが多い道を歩きますから、大丈夫ですよ!」
「そう……? なにかあったら大きな声で助けを呼ぶのよ?」
「はい! 大声には自信ありますから、任せてください!」
ぐっと力こぶをつくると、藍雪さまは笑ってくれた。
「芽衣の声はよく通るものね。でも無理しないように。いってらっしゃい」
「いってきます。藍雪さまもお仕事がんばってください!」
こうやって藍雪さまと別行動することはさびしいけど、ちょっとずつ慣れてきた。
お互いにやれることをやらなきゃだね。
では、今日も花殿へおじゃまします!
人が多い道を選んで花殿に行くと、部屋からいい香りがただよってきた。
胸がすっきりするような、すてきな香りだ。
「おはようございます。わあ、百命花だ!」
部屋の中には、淡い黄色の花がたくさんあった。
そんな花のあいまから、ひょっこりと杏が顔を出す。
「芽衣、久しぶり。元気だった?」
「杏! やっほー、会いたかったよー!」
「わっ、ちょっと、もう。芽衣はあいかわらずだね」
走っていって、ぎゅーっと抱きつけば、杏はくすくすと笑った。
杏は、髪を頭の上でひとつにまとめている、後宮の宮女仲間で友だちだ。
「ね、里帰り、楽しかった?」
「楽しかったよ。母さんの具合もよくなってるみたいだし」
そっかそっか、それならよかった。杏のお母さん、病気がちだもんね。
実は、杏の育った村は百命花を育てていて、今回の儀式に使う花を用意していたんだって。杏も花の世話のために、しばらく後宮をはなれていたんだ。
ここにある花も、杏が届けてくれたみたい。
ふと、杏が真剣な雰囲気になって、わたしからはなれた。
「紅花さま。舞手が活けた花を『百命花の舞』の会場に飾ることが習わしだそうです。ここにある花を使ってください」
「……ええ」
椅子に座っていた紅花さまは、つんとそっぽを向きながらうなずく。杏も緊張した顔だから、落ち着かない空気が流れた。
……このふたりも、后選びのときにいろいろあったもんね。
「あなた、髪を結んでちょうだい」
「あ、はい」
わたしは紅花さまの赤い髪をひとつに結んだ。
髪型がすっきりした紅花さまは、真剣に花を選んで、花瓶に活けていく。
「でも、杏。いまから活けて、儀式当日までもつのかな?」
「百命花は長持ちするんだよ。儀式は一週間後でしょ。よゆうだと思う」
「……もう、一週間後かあ」
忙しすぎて忘れてたけど、あとすこしで本番なんだね。うう、緊張するかも。
「わたしね、『百命花の舞』がすごく楽しみなんだ」
杏がわたしを見て、目を細めた。
「ほら、あの儀式って病気平癒の祈りがこめられてるでしょ? わたしの母さんは流行り病ってわけじゃないんだけど、でも舞がうまくいったら、母さんも元気になるかなあ、なんて思って」
「杏……」
そっか。そうだよね、たしかに『百命花の舞』はそういう儀式だった。
白竜さまと藍雪さまが、やさしい気持ちで開くもの。
その儀式を心待ちにする人がいるんだ。
杏だけじゃない、国中にきっともっと、たくさんいるんだよね。
――ということは、わたし、すごく大切な役目を背負ってる?
「責任重大だなあ」
わたしはいままでずっと、「うまく舞いたい」って思ってた。
だけど、うまいだけじゃ、だめなのかもしれない。
「舞手は、自分じゃなくて、みんなのために舞うものなのかもしれないね」
白竜さまと藍雪さまの想いを抱えて。
大切な人が病から回復してほしいっていう、みんなの想いを抱えて。
そうして舞うのが、きっと『百命花の舞』なんだ。……よし、がんばろう!
「――みんなのためとか、そういうの、わたしにはよくわからないわ」
紅花さまが作業の手を止めないまま、つぶやいた。
「他人なんてどうでもいいもの」
百命花の茎をぱちっぱちっと、はさみで切っていく紅花さま。
どうでもいいなんて、いじわるだ。でも――、本当にそうなのかな?
まわりの期待に応えたいって思う紅花さまは、みんなのことをしっかり考えてる気がするんだけど……。
杏は無言になってから、紅花さまを見つめた。
「わたし、紅花さまの舞も楽しみです。儀式を、どうか成功させてくださいね」
紅花さまは一度杏を見て、居心地が悪そうに目をそらす。
「母親の病気平癒を、よりにもよってわたしに頼むの?」
「后選びのとき、紅花さまにされたことはつらかったし、わたしもたくさん反省しています。でも今回の紅花さまは、真面目に舞を披露されるんでしょう? だったら、わたしは応援します」
杏の声は、すごくまっすぐな響きをしていた。
紅花さまはすこししてから、ふんっと鼻を鳴らす。
「言われなくても、わかってるわ。ほら、花はこれでいいでしょ」
わ、すごい!
花瓶にはすっごくきれいに、百命花を中心とした花たちが活けられていた。
杏もほれぼれしてため息をついてから、うなずく。
「では、その花瓶を宮廷まで届けていただけますか? 役人に届けるまでが、舞手の仕事だそうなので」
「まったく、面倒ね。あなた、花瓶を持ってちょうだい」
え、わたし⁉
「あなたも一応、舞手でしょ。仕事をしなさい」
「う……、わかりました」
よいしょっと、花瓶を持ちあげる。結構重いんだけど……!
そのまま、わたしと紅花さまは杏と別れて、馬車で移動した。
ゆれるときに花瓶を落とさないように気をつけなきゃ。
緊張してるわたしとは反対に、紅花さまは窓枠に肘をついて外を眺めていた。
「ねえ。衣装はもうできたの?」
視線は外に向けたまま、紅花さまが聞いてくる。
「あともうすこしで完成しますよ。さすがに三着同時進行は疲れますね」
「三着?」
「『百命花の舞』の紅花さまとわたしと、藍雪さまの分。あ、でも藍雪さまの婚礼の衣装もつくっているので、四着同時進行ですね」
「……呆れた。仕事のしすぎは禁物よ。疲れて倒れる前に、うちの侍女に言いなさい。あの子たちもひと通りの裁縫ならできるから」
「え」
ぽかんとしたわたしを、紅花さまは「なによ」と眉を寄せてにらんできた。
「あの、いまのって、わたしのことを心配してくれたんですか?」
「……はあ⁉ してないわ! 変なこと言わないで!」
うわっ、急に大きな声を出さないでほしいな……!
「わたしはただ、衣装づくりが間にあわないとか、寝不足で適当につくったとか、そういうことにならないようにって言ってるの!」
「ああ、なるほど」
最近、前ほどつんつんした態度をしてこないから、同じ舞台に立つ舞手として認めてもらえたのかなあ、なんて思ったんだけど。ちがったのかな。
「あと、侍女に手伝わせていいのは、わたしとあなたの衣装だけよ。藍雪の分なんて、知ったことじゃないわ」
ふんっとそっぽを向く紅花さま。うんん……、あいかわずだ。でも、いいよ。
「藍雪さまの衣装は自分でつくりたいので、大丈夫です」
これだけは、だれにもゆずりたくないからね。
「……どうして、あなたはそこまで藍雪が好きなの?」
ふいに、そう聞かれた。どうしてと言われても。
「やさしいし、かわいいし、笑顔がすてきだし、まっすぐで強い心を持ってるし――、長くなりますけど、全部聞きます?」
「……結構よ」
えええ、残念。大好きな藍雪さま語りができると思ったのに。
(でも、紅花さま、なんでそんなことを?)
ため息まじりにもう一度外を見ている紅花さまは、いつもよりちょっとだけ元気がないように見えた。
「どうかしたんですか?」
「べつに」
結んだ髪の毛先をくるくると指でいじる紅花さまは、やがて、口を開く。
「――うちの侍女たちは、そこまでわたしを好きではないだろうな、って思っただけよ」
「侍女さんたち?」
「わたしといっしょに舞うことすら、嫌がらせを怖がってできないくらいだもの。……主人としておとっているのかと、自分がなさけなくなってくるわね」
ぽつん、と紅花さまのつぶやきが落ちた。でもすぐに、首をふる。
「あなたが主人自慢をするものだから、変なことを口走ったわ。いまのは忘れなさい。いいわね?」
念を押すみたいに、するどくにらみつけられる。
――もしかして紅花さま、さびしいのかな。
紅花さまにとっても、今回の『百命花の舞』は一筋縄ではいかない儀式だよね。
嫌がらせをされて、だれも助けてくれなくて……。
そんな状況だったら、弱気にもなっちゃうかもしれない。
うーん、だけどわたし、思うんだ。
「紅花さまは侍女さんたちに好かれていると思いますよ」
「……ちょっと、わたしの話を聞きなさい。さっき、忘れろって言ったのよ」
「はい、このあとでちゃんと忘れますよ。だからもうすこし、お話しませんか」
紅花さまはぽかんとわたしを見る。
弱っている子って、放っておけないよね。
「ねえ、紅花さま。舞の衣装をつくってほしいって最初にわたしに頼んできたのは、侍女さんでしたよ。わたしの舞の練習につきあってくれているのも、侍女さんたちです。それって、全部紅花さまのためですよね」
紅花さまって、実は、自分の侍女にきつく当たることはほとんどないんだ。
侍女さんたちも、紅花さまのためにってがんばってるし。
そんなに悪い関係には見えないんだよね。
(まあ、后選びのときのわたしは、散々紅花さまや侍女さんにきついことをされたから、簡単に「いい人たち!」とは言い切れないんだけど……)
それでもたぶん、紅花さまと侍女さんたちには、ちゃんと信頼がある。
「自信を持ってください……、ほどほどに! 自信持ちすぎて、まわりの人を見下すのはだめですよ? ほどよく自信を持ってくださいね!」
紅花さまの眉がぎゅっとよった。
「それ、なぐさめているのか、けんかを売っているのか、どっちなの?」
「なぐさめてます!」
「……まあいいわ。そういうことにしてあげる。というか、あなたごときがわたしをなぐさめるなんて、調子に乗らないでちょうだい!」
「あ、ほら! さっそくわたしのこと見下してるじゃないですか!」
わたしを鼻で笑った紅花さまは、持っていた扇を開くと口もとを隠した。
澄ました顔しちゃって、もうー!
「……ねえ、本当に、いま話したことはすべて忘れるのよね?」
「忘れますよ。でも、傷ついているわたしの心は忘れられないかもです!」
「あらそう。……どうせ忘れるなら、もうひとつだけ聞いておくわ」
あ、軽く流された。また傷つきましたよ、わたし!
でも紅花さまがちょっと真剣な目になったから、わたしも背筋をのばす。
「――藍雪は、わたしが嫌がらせをしていたとき、どんな様子だった?」
藍雪さま……? それは、もちろん。
「とても悲しかったし、つらかったと思います」
紅花さまは視線を落として「そう」とつぶやいた。
もしかして、自分が嫌がらせをされる立場になって、あのころの藍雪さまの気持ちがわかるようになってきたのかな。……そうだといいな。
紅花さまにはそういうことを、ちゃんと知ってほしい。
そうじゃないと、なにも変わらないと思うから。

