


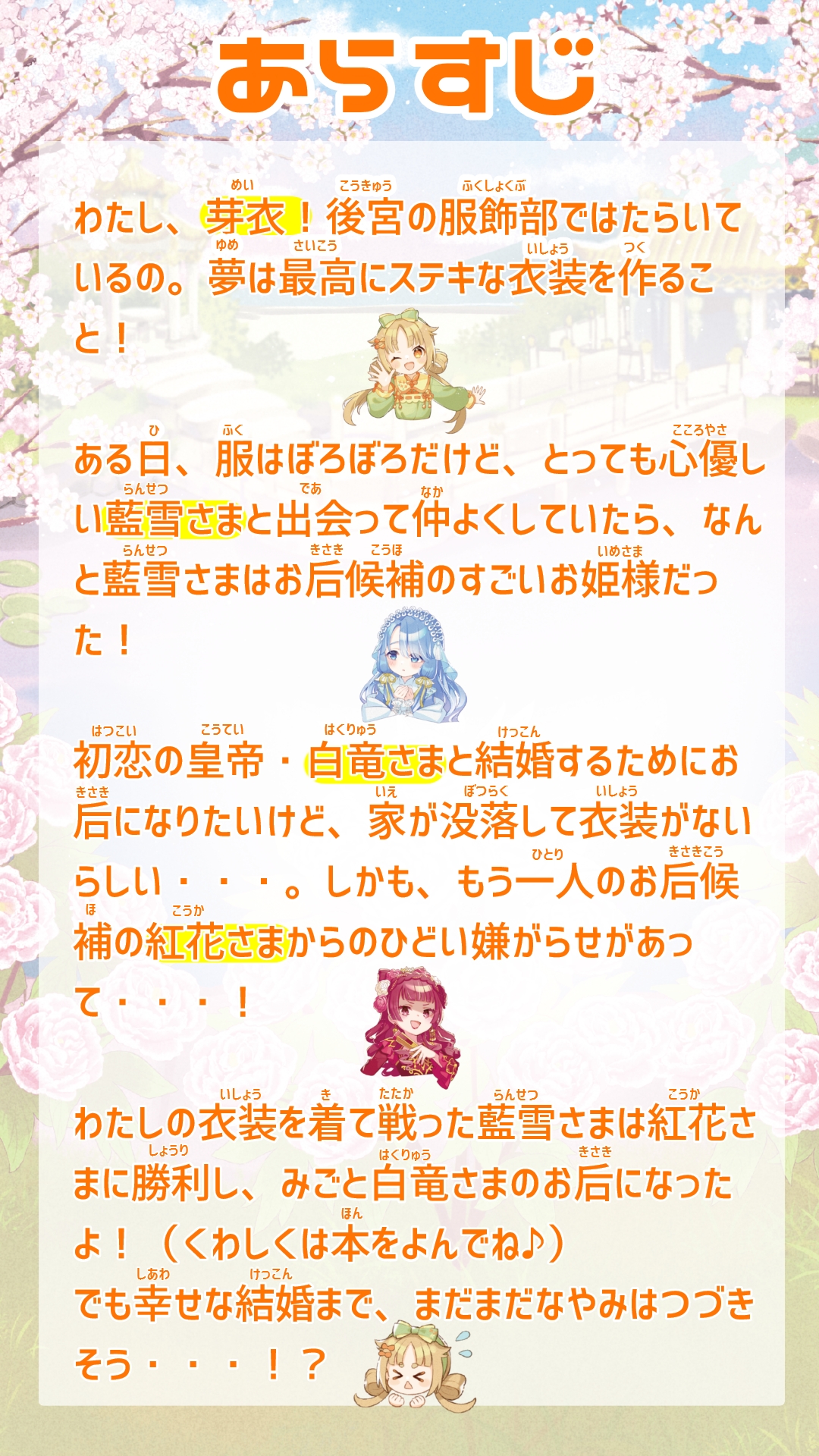


第2章
数日後、わたしと藍雪さまは宮廷に呼ばれていた。
もちろん、わたしたちを呼んだのは白竜さまだ。
王さまの執務室で待ち構えていた白竜さまは、藍雪さまにさっそく切りだした。
「今年の『百命花の舞(ひゃくめいかのまい)』だけど、藍雪に舞手を決めてほしいんだ」
「わたしに?」
「うん。姫をまとめているのは藍雪だからね。だれが適任か教えてほしい」
藍雪さまは「そうですね……」と難しそうな顔でうつむく。
『百命花の舞』は毎年ふたりの姫が舞を披露する儀式なんだって。
その姫を選ぶのは、王さまとお后さまだ。
藍雪さま自身は儀式を取り仕切る側だから、舞手にはなれない。
だから藍雪さま以外で、舞が上手なお姫さまを選ぶ必要があるらしい。
「……ひとりは、紅花が適任ではないでしょうか」
すこしして、藍雪さまが心を決めたみたいに顔を上げた。
(まあ、舞が上手な姫っていったら、そうなるよね)
后の立場をかけて、藍雪さまと争っていた紅花さま。すごく美人で努力家で、舞も琴も得意なんだけど、とにかくいじわるなんだよ……。
「白竜さまは、今年の儀式に力を入れたいとお思いなんですよね? だったら、きっと紅花が適任ですわ」
「……そっか、藍雪にはお見通しだったんだね」
白竜さまははずかしそうにほほをかいた。藍雪さまは眉を下げて笑ってる。
(藍雪さま、またさびしそうな顔だ……)
儀式の話をすると、そういう顔をするんだよね。なんでかな。
ふと、藍雪さまと目が合った。
「芽衣は『百命花の舞』をくわしく知らないのよね?」
「す、すみません……。初耳です。宮廷って儀式多すぎですよ!」
「もう。『百命花の舞』はね、病気平癒の祈りをこめたお祭りなの」
「病気平癒……、『病気治ってくださーい!』ってことですか?」
「そう。この国では最近、病が流行っているでしょう? わたしの両親も、白竜さまのお父さまも、そのために亡くなったわ」
あ……。そうだった。藍雪さまも白竜さまも、家族を亡くしてるんだよね。
「流行り病が収まるように、白竜さまはこの儀式を大切にしたいと、そう思っていらっしゃるんじゃないかしら」
藍雪さまの言葉に、白竜さまは深くうなずいた。
「いつもなら儀式は宮廷の建物で開催して、貴族だけが見物するものだけど、今回は民も見に来られるようにしようと思ってる。きっと、きれいな舞を見たら、みんなの心も晴れるだろうから」
白竜さま……。
たしかに、病気が流行っていると、みんな悲しい気持ちになる。
藍雪さまが儀式の話を聞いてさびしそうだったのは、両親のことを思い出していたからかな。白竜さまも、同じ気持ちなのかもしれない。
でもだからこそ、この儀式を成功させたいって思ってるのかも。
もう病で苦しむ人がいなくなるように。みんなが明るくなれるように――。
「百命花は薬として、病の治療にも使われるんだ。儀式の会場を飾った花は、後日民にも配ろうと思ってる。ちなみに、これがその百命花だよ」
「わ……、きれいな花ですね!」
白竜さまは窓辺に活けられていた花を一輪、手にとった。淡い黄色の花だ。
六枚の花びらが根本から先端にかけて広がっていく見た目は、百合の花みたい。透けそうなくらい淡い色合いのその花は「清らか」って言葉が似合う。
「百命花は高価で民の手に渡りにくいから、すこしでも配りたいんだ」
そっか。白竜さまは舞でみんなを元気にしながら、薬もくれるんだね。
「やさしい王さますぎる。さすが、藍雪さまが好きになるだけありますね!」
「え、あ、ちょっと、芽衣!」
……はっ! しまった。つい、ぽろっと言っちゃった。
藍雪さまは耳まで真っ赤に染めて、「はずかしいこと言わないで……!」ってあわててる。ああ、恋する乙女の藍雪さま、かわいい。大好き!
って、そうじゃなくて。ごめんなさい、悪気はないんですーっ!
「あいかわらず、ふたりは仲がいいね。藍雪に好きだと思ってもらえているのなら、ぼくもうれしいよ」
白竜さまはにこにこと笑ってる。そのせいで、藍雪さまはもっともっと真っ赤になって、両手で顔を隠しちゃった。うん、かわいい!
しばらくして、藍雪さまは、こほんと咳払いをする。
「と、とにかく! 儀式成功のために、舞は紅花に任せるべきですわ。もうひとりの舞手は、紅花自身に決めさせてみてはいかがでしょうか」
――そのときだった。
「それは光栄ですね。娘を評価してくださり、ありがたいことです」
扉が開いて、男の人が入ってきた。……だれだろう?
背が高くて、がっしりとした男の人だ。濃い赤色の衣装はぱっと見でもわかるくらい高価な布を使っているし、その男の人に似合ってる。
でも、この衣装の感じというか、雰囲気というか、見覚えがある気が……。
「――あの方は、紅花の父上よ。役職で言うなら、大臣ね」
藍雪さまがわたしにだけ聞こえるように耳打ちしてくれた。
へえ、大臣……って、待って! この人が紅花さまのお父さん⁉
藍雪さまのお家の仕事を乗っとって、藍雪さまを貧乏にさせたのが、この人ってこと⁉ うわさの、いじわるお父さん!
「大臣、急ぎの用件かな? ぼくは藍雪と話しているのだけど」
白竜さまはちょっと眉をひそめたけど、大臣は気にしない様子で笑った。
「ええ、大切なお話です。お時間をちょうだいできますかな?」
「……わかった。藍雪、今日はもう休んでいいよ。来てくれてありがとう」
白竜さまが藍雪さまに言って、表情をやわらかくする。
「舞手はきみの言うとおり、紅花に任せよう。それから、藍雪にはこれからも儀式の準備を手伝ってもらうと思うけど、いいかな」
藍雪さまは「もちろんです」ってうなずいてから、扉の方へ向かった。
わたしもそれにつづくんだけど……、なんだかなあ。
ちらっと見ると、大臣はわたしたち――というか、藍雪さまを値踏みするみたいに見ていた。なんか嫌な感じ。
「藍雪さま、早く帰りましょう!」
戸惑う藍雪さまをぐいぐいと押して部屋を出る。
そのまま馬車を待たせている場所まで、外廊下を歩いていった。
せっかく白竜さまに会えて幸せ気分だったのに、台無しだよ……。あ、でも。
「『百命花の舞』、楽しみですね。お花、すっごくきれいでした!」
「そうね。舞も美しいのよ。紅花ならだれよりも完ぺきに舞うでしょうし」
……うーん、紅花さまかあ。たしかにきれいな舞だろうけど。
さっきの大臣のこともあって、ちょっと微妙な気持ちになっちゃう。
「わたし、藍雪さまの舞も見てみたかったです」
「え?」
「藍雪さまの舞なら、絶対かわいいですもん! 辰の国一! 天女顔負け!」
「そ、それは言い過ぎじゃないかしら……?」
藍雪さまは顔を赤くして、はずかしそうに笑った。
ほら見て、このかわいさ! きらきらしてる! そんな藍雪さまがかわいい衣装を着て舞ったら、ときめきが止まらないと思うんだよね!
「きっと藍雪さまが舞ったら、白竜さまももっと藍雪さまを好きになりますよ」
「え――、そうかしら?」
藍雪さまが、ぴたっと立ちどまった。
と思ったら、わたしにぐいっと顔を寄せてくる。
「そう思う? 本当に? 白竜さまに、好きだと思ってもらえるかしら?」
わたしがにぎっていたはずの手が、いつのまにか藍雪さまににぎりかえされていた。真っ赤な顔で真剣に聞いてくる藍雪さま――。
(いや、かわいすぎるのでは! 乙女!)
そうだよね、好きなひとにはもっともっと好かれたいよね!
でも藍雪さまはすぐ思い直したみたいに、真面目な顔になる。
「まずは『百命花の舞』よ。后として、王を支えないと」
「そうでした。久しぶりの大きな儀式ですもんね。がんばりましょう!」
「ええ!」
后選びのつぎは、『百命花の舞』。楽しみだね!

