


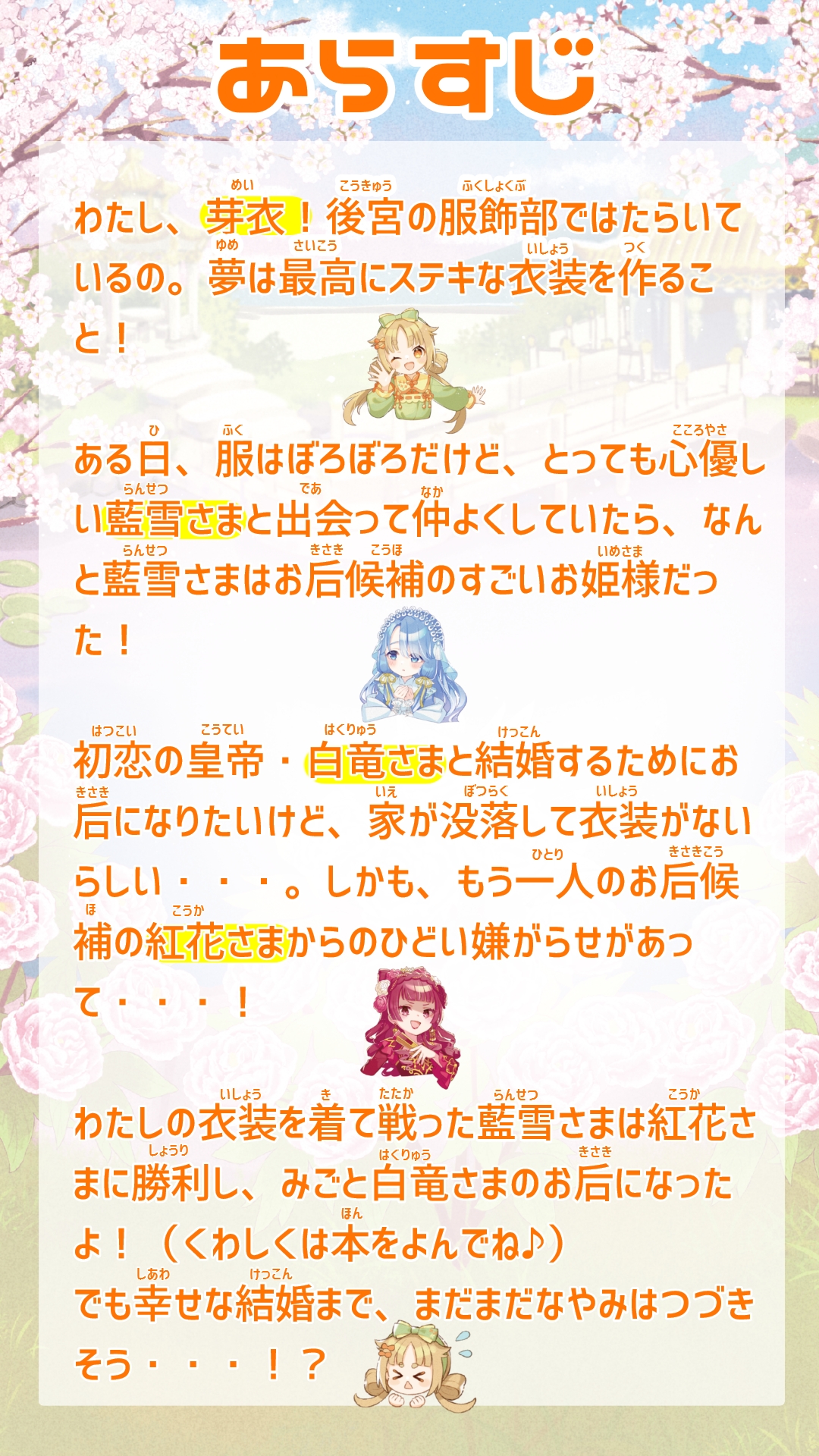


第●章
側室選びなんて大問題が浮上しても、時間は進む。
ついに『百命花の舞』当日がやってきた。……やってきちゃった。
(わたし、舞ってもいいんだよね?)
あれから、藍雪さまとはまともに話せていない。もしかしたら、わたしは舞手を辞退するべきなのかもしれなかった。でも、できない。
それは藍雪さまのためにならないって、そう思うから。
わたしと紅花さまはもう支度を整えて、会場の入り口で待機している。
「……すごい人ですね」
今回の儀式は、宮廷の中にある屋外広場で行われる。
きらきらした日差しを浴びた、すりばち状の広場だ。
中央に舞を披露する舞台があって、前方には王と后の席。まわりには階段状に見物席がずらーっとつくられている。下の方の席には貴族、上の方の席には町から来た人たちがいるみたい。
となりにいた紅花さまがふんっと鼻を鳴らした。
「なに? いまさらおじけづいたの? 逃げたかったら逃げてもいいわよ」
「……いいえ、いまさら逃げません」
逃げちゃだめだ。しっかりしなきゃ。
「――側室の話、聞いたんでしょ。あなたは逃げるんじゃないかと思ってた」
はっとして、紅花さまを見る。紅花さまは静かな表情だった。
やっぱり、紅花さまも側室のことを聞いていたんだね。
「迷っているくらいなら、辞退しなさい。中途半端な舞をされても迷惑よ」
「そ、そんな、ちゃんと舞いますよ……! そりゃあ、複雑な気持ちですけど」
「あら、そう。――あなた、藍雪のことを信用できなくなったのね」
「……はい⁉」
紅花さまはうでを組んで笑ってる。な、なに言ってるの⁉
「だってそうじゃない。わたしが側室になったら、藍雪が白竜さまに愛されなくなるかもって心配してるんでしょ? まあ当然よね、わたしは最高の姫だし」
「なっ……! そんな心配してません! それに最高のお姫さまは藍雪さまです! 紅花さまもすごいのは認めますが!」
でもでも、わたしは藍雪さまが一番だと思ってるよ!
「――だったら、自信を持ちなさい」
ぴしゃりと、紅花さまが言った。
「なにがあろうと、自分の主人が一番だと思えばいいわ。このわたしが相手でも、藍雪の方が白竜さまに愛されるんだって言い張りなさい。侍女から信用されなくなったら、主人は終わりよ。せめてあなたは、藍雪を信じなさい」
「え……」
な、なんか、紅花さまの言葉がすごく心に響くんだけど……。
まじまじと紅花さまを見ちゃう。紅花さまはふっと笑った。
「ついでに、自分のことも信じるといいわ。あなたなら、大丈夫」
「……へ?」
「うちの侍女と、わたし自ら、たっぷり時間をかけて稽古をつけてあげたんだから。舞台で無様な姿をさらすようなこと、あるわけないもの」
こ、紅花さま……、もしかして、はげましてくれてる⁉ あの紅花さまが⁉
「――というわけで、しっかり舞いなさい。失敗したら容赦しないから」
あれ。
急につんとした表情にもどった紅花さま。あ、なんかこれって「失敗させないために、とりあえずはげまそう」くらいの会話だったのかも。
じーんとしてたのに、感動台無しだよ……!
でも、すっきりした気がする。
側室がいようと、藍雪さまが一番に決まってるんだ。
だから、わたしが迷う必要はないのかもしれない。わたしは藍雪さまを信じてるし、これからも藍雪さまが白竜さまの一番でいられるように支えていく。
だから、大丈夫。これくらいの壁はなんともない、のかな……?
ぐっと、こぶしをにぎる。
わたしが辞退して紅花さまを困らせたら、藍雪さまはきっと一生後悔すると思うんだ。
いまはよくても、藍雪さまの心に傷が残って消えなくなると思う。
わたしは、そんなことをしたくない。
「……ありがとうございます、紅花さま。わたし、がんばります。今日はとっておきの衣装もあるし、絶対、舞を成功させましょう!」
「そうね。まあ、この衣装はいい出来だと思うわ」
「え」
紅花さまが、素直にほめてくれた⁉ ……え、今度は素直にほめてるよね?
衣装のすそを持ちあげる紅花さまは楽しそうだし。
うん、これは素直なほめ言葉だ! ということは。
「どうしたんですか! わたしをほめるなんて、なにか変なもの食べました⁉」
「……はあ⁉ なによ、わたしがほめたら悪いの⁉」
「いいえ、うれしいです! もっとほめてください!」
紅花さまが「あなたねえ」ってほほをひきつらせる。前までだったら怖いと思ったかもしれない表情だけど、花殿に毎日通ったおかげでもう慣れてきたよ。
わたしは紅花さまのとげとげした視線を気にせず、胸を張る。
新しい衣装を着ている今日のわたしは、最強のはずだ。
化粧も髪も、ばっちり気合いを入れてきたし。
「もはや舞が成功する未来しか見えません! この衣装で、会場のみなさんを魅了しちゃいましょう!」
「衣装の話になるとすぐ元気になるじゃない。単純ね」
「衣装が大好きなので! あ、そういえば、琴の演奏をしてくれるお姫さまの衣装って、準備しなくてよかったんですか?」
「ああ、それは彼女に任せておけばいいわ。あの子だって姫だもの。うまくやるでしょう。本人も『こちらのことはお気になさらず』って言っていたから」
へー、そうなんだ。
あのお姫さま、今日はまだ会ってないんだよね。もう中にいるのかな?
実はちょっと、あのお姫さまに関しては不安なんだけど……。
ごおおおおおん
鐘の音が響いた。その音で、会場の空気が変わる。
そわそわが高まるような、ぴりっと背筋がのびるような、独特な空気だ。
後ろから衣装のゆれる音がした。
「おはよう、紅花、芽衣。今日はよろしくね」
わたしと紅花さまはふり返る。
「白竜さま!」
そこにいたのは疲れた顔の白竜さまだった。やっぱり、まだ悩んでるのかな。
それから――、白竜さまのとなりには藍雪さまも立っていた。
藍雪さまと紅花さまは一瞬視線を合わせて、すぐに目をそらす。
うう、空気が重い。でも、もう逃げない。
「藍雪さま。かんざしの位置を直してもいいですか?」
わたしは藍雪さまに近づいて、きれいな青い髪にかんざしをさし直した。
后選びのときに、白竜さまから贈られた銀のかんざしだ。
「はい、できました。これで完ぺきな『お后さま』です」
朝、支度を手伝ったときにも思ったけど、今日の藍雪さまは本当にきれいだ。
「……芽衣」
不安そうな顔で見つめられて、わたしは深呼吸をする。
「わかってますよ、藍雪さま。でも、わたしは藍雪さまを信じていますから」
「え?」
「どんな状況になっても、藍雪さまは最高のお姫さまで、お后さまです」
藍雪さまは衣装を見下ろす。わたしがこの数日で仕上げた衣装だ。
「『お后さま』……、やっぱりこの衣装は、そういうことなのね」
「はい。だから、いってらっしゃいませ、藍雪さま。みんなに、藍雪さまがお后さまなんだってことを示してきてください」
「……あなたは、本当に舞うの?」
つらそうな藍雪さまの表情に苦しくなるけど、「はい」って深くうなずく。
ごめんなさい。だけど、きっとこれが藍雪さまのためだって思うんです。
「藍雪、行こう」
白竜さまが手を差しだして、藍雪さまはその手をとって歩きだす。
会場に入ったとたんに拍手があふれて、ふたりを包みこんだ。
(すごい。藍雪さまたち、めちゃくちゃ歓迎されてる)
拍手の合間に「きれい!」「待ってましたわ!」って、たくさんの声が聞こえてきた。
それから、「あの衣装、すてき!」「『お后さま』だ!」って声も。
そうだよ、ただひとりのお后さまは、藍雪さまなの。
「――あの衣装、婚礼の衣装に似せてつくったのね」
紅花さまが静かに聞いてきた。
「はい。まあ、似せてというより、もともと婚礼の衣装用につくっていた衣装を改造しただけなんですけど」
王さまとお后さまの結婚には、たくさんの儀式がある。
とくに神さまに結婚を報告する儀式では、決められた衣装があったよね。
下衣の後ろのすそを長くのばした、特別な白い衣装だ。
いま、藍雪さまは純白の長いすそを引いて、会場をゆったりと歩いている。
すそには銀糸で細かい刺しゅうを散りばめて、銀の宝石もたくさんあしらった。
そんな衣装が、夏の日差しに夢みたいに輝いている。
現実とは思えないような、豪華でせんさいできれいな藍雪さまの姿は、だれだって見とれちゃうよね。
「実際の儀式で使う衣装より、すそは短くしました。それは本番にとっておきたいから。今日使っちゃったから、婚礼の衣装は一からつくりなおしですけどね」
だけどどうしても、この衣装を着てほしかった。
純白のすその長い衣装は『お后さま』の象徴だもん。
もし紅花さまが側室になっても、白竜さまが選んだ后は藍雪さまだけ。
それを示す衣装にしたかった。
きっといま、会場のみんなの心に「『お后さま』、すごくきれい!」って思いが刻まれているはずだ。……これですこしは、藍雪さまの助けになれたかな。
ふっと息をして、わたしは紅花さまに向きあった。
「紅花さまは、側室になりたいんですか?」
「……さあ。でも、藍雪に遠慮なんてしないわ。本気でいくわよ」
はぐらかされた。まあ、いいよ。やることは変わらないし。
ごおおおおおん
もう一度、鐘の音が鳴る。これは、わたしたちが入場する合図だ。
「みんなのために、舞いましょう!」
大切な人に元気になってほしいって願う、この儀式。
わたしもみんなのために、やさしい気持ちで舞うからね。
「……あなた、あの日から舞い方がすこし変わったわね。その甘い考えが、いい影響でも与えているのかしら。まったくもって、理解できないわ」
苦々しそうにつぶやく紅花さま……、えーっと、一応ほめてくれてる? 前よりきれいに舞えてるってこといたいっぽいし。
たしかに、あれから、ふりつけがぴたっと体になじむような感覚があった。
「紅花さまも、同じ気持ちで舞台に上がりませんか?」
「無理よ。わたしはやさしくないもの」
紅花さまは肩をすくめて、すぐ前を向きなおす。
「でもまあ、参考程度には頭に入れておいてあげる。さあ、行くわよ」
「……はい!」
なにはともあれ、ここからが本番だ。

