


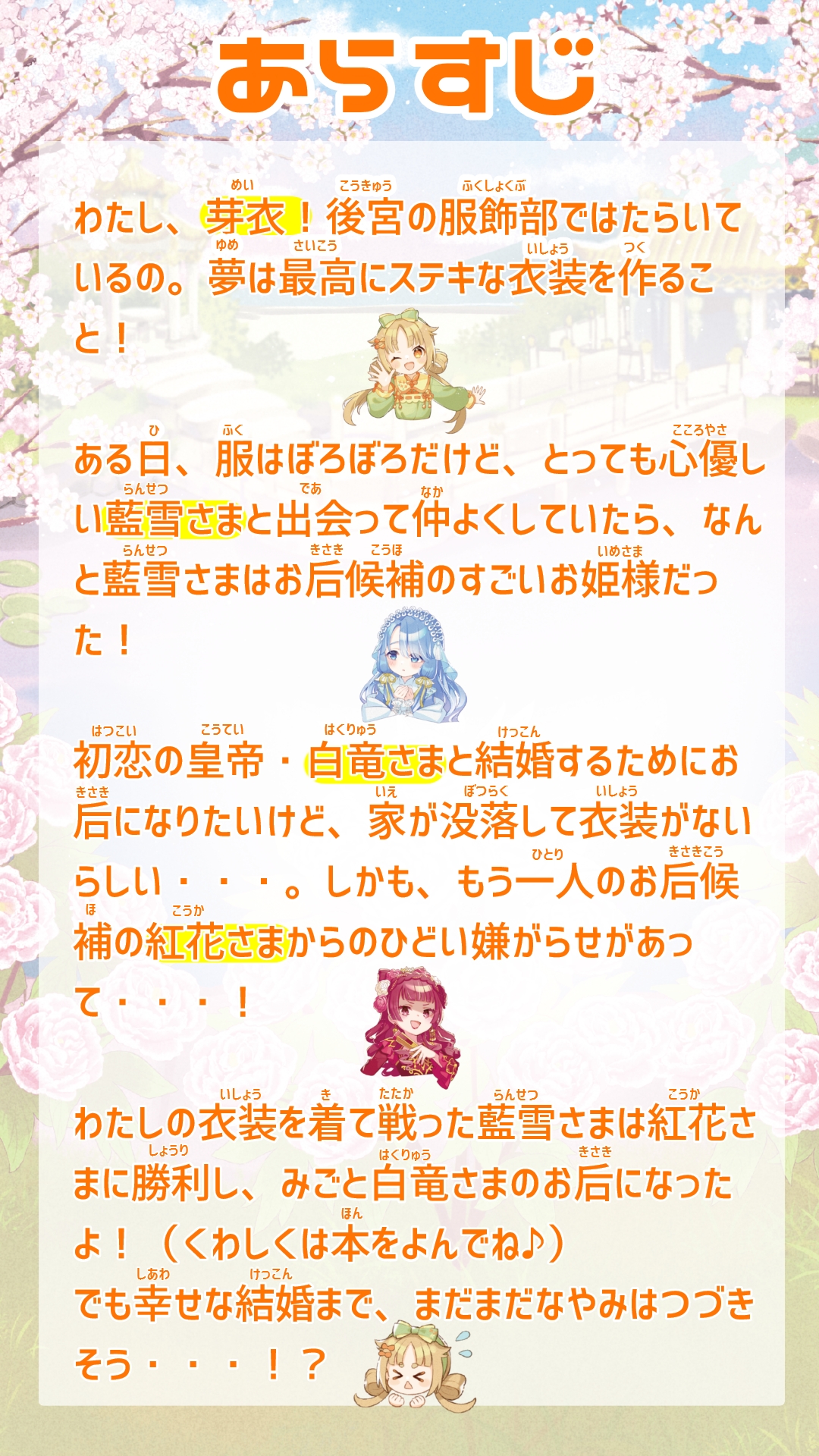


第6章
「って、ぜんっぜん、だめじゃない! へたすぎるわ! ありえない!」
どっかーん、と紅花さまの雷が落ちた。どこにって、もちろんわたしの上に。
「すみませんっ! 本当に、ごめんなさいっ!」
わたしはもう平謝りするしかなくて、泣きながら、ぺこぺこ頭をさげる。
けがをした侍女の代わりにわたしが舞うって決めてから、さっそく舞の練習をすることになった……、んだけど。
侍女たちに教えてもらって数時間が経過しましたが、とってもまずいです。
(わたし、舞の才能がなさすぎる……⁉)
音楽に体がついていかない。ふりつけが覚えられないし、転んじゃう。
お、おかしいな……? もうちょっと、できると思ったんだけど。
「あなた、本当にわたしと並んで舞う気があるの⁉」
「ありますよ、ありまくりです! でもほら、まだ初日なので……」
「ふりつけなんて、一回見れば覚えられるでしょう!」
「無理ですよ、そんなの!」
紅花さまは鬼の形相で「本気でやりなさい!」と雷を落として去っていく。
そのあとも、侍女たちが舞を教えてくれたけど、今日の成果はほとんどなし。
天陽宮の近くに帰ってくるころには、もうすっかり夜だった。
(疲れた。遅くなっちゃったし……。舞、藍雪さまに教えてもらおうかな)
でも藍雪さまは后のお仕事で忙しいよね。
「芽衣、おかえり」
「わっ! え、雷斗さま?」
天陽宮の前にいたのは、片手をあげた雷斗さまだった。
「どうしたんですか、そんなところで」
「兄上のお使いで、藍雪どのに会いにきたんだ。そっちの仕事は終わったんだが、芽衣がまだ花殿から帰ってきてないって聞いたから、待ってた」
「え、わたしに用事でもありましたか?」
「用事ってほどじゃない。でも、紅花どのの衣装づくりを引きうけたんだろう? 順調か?」
もしかして、雷斗さま、心配してくれたのかな?
や、やさしい……! 疲れた心にしみわたるよ!
思わず涙目になると、雷斗さまは目を見開いてから、苦笑した。
「やっぱり、いろいろ大変だったみたいだな。大丈夫か?」
わたしたちは天陽宮の庭を歩きながら、話をつづけた。
「実は、衣装づくりだけじゃなくて、舞手もすることになって」
「そんなことが……。芽衣のまわりは、あわただしいな」
「でも、ふりつけがもう頭から抜けちゃってるんですよ。うう、もう一回、見せてもらいたい。もう夜だから無理ですけど」
「ああ、それなら任せろ。芽衣、舞に使う扇は持ってるか?」
扇? それは持ってるけど……。
花殿の侍女たちが貸してくれた扇を見せると、雷斗さまはそれを受け取って、庭の開けた場所に歩いていく。月明かりが差す場所で、ふり返った。
「女性の舞は専門外だけど、まあ、ふりつけくらいなら覚えてるからさ」
にっと笑って、雷斗さまは扇を構えた。
って、うそ、まさか……。
ふわっと、雷斗さまが足を踏みだす。
しなやかな手足がたどるのは、『百命花の舞』の動きだ。落ち着いた声で旋律を口ずさみながら、雷斗さまは音に合わせて舞を披露する。
(わあ……っ!)
紅花さまの舞と同じようで、でもぜんぜんちがった。
紅花さまは清楚で清らかな舞だったけど、雷斗さまには芯の強さみたいなものがある。
ひとつひとつの動きが大胆で、でもまっすぐで、きれいで。
雷斗さまの黒い衣装にあしらわれた金細工が、月明かりにきらきら輝く。
――かっこいい。
「と、まあ、こんな感じだ。復習にはなったか? って、芽衣?」
「えっ、あ、えっと、はい⁉」
「いや、だから、ふりつけは思いだせたか?」
「あああっ、はい! たぶん! いや、え? どうかな⁉」
まずい、ぼーっとしてて、練習のこととかなにも考えてなかった!
「だれのために舞ったと思ってるんだよ」
雷斗さまがあきれた笑いを浮かべて、わたしに扇を返してくる。
うう、心臓ばくばくしてる。平常心、平常心……!
「えっと……、雷斗さま、舞が得意だったんですか?」
「教養として学んだだけだよ。一応、これでも王族だからな。……もう一回見せたほうがいいか? 心ここにあらずみたいだったし」
はずかしい。見とれてました、なんて言えないよ!
わたしは、ぶんぶん首を横にふる。
「雷斗さまの舞は心に刻みましたので、あとは思いだしながらやってみます!」
「そうか。芽衣は、やって覚える方が向いてるのかもな。……でも」
でも?
「ひとりより、ふたりの方がいいだろ。まだすこし時間があるから、俺でよければ指南役をするけど。どうする?」
それって、雷斗さまが教えてくれるの? いいのかな? ぜいたくすぎない?
だけど、雷斗さまがそう言ってくれるなら……。
「ぜひ、よろしくお願いします!」
了解、と笑った雷斗さまは、わたしの練習にずっとつきあってくれた。
でも、やっぱりうまくいかない。
生まれてからずーっと、舞なんてやったことないからね。
「もう、だめ……!」
足がぷるぷるすぎて、地面に倒れた。これ以上、動けません!
「おつかれ。まあ、すこしは上達したんじゃないか?」
「え。ほんとですか⁉」
「……あー、まあ、たぶんな」
苦笑する雷斗さま。なるほど、気をつかってくれているっぽい。
「すみません、もっと、がんばりますね」
「無理はするなよ。でも、そうだな――、舞が苦手だと思うなら、舞っているとき、意識をほかのことに向けてみるといいんじゃないか?」
「ほかのこと……?」
「たとえば、衣装のことを考える、とかさ」
「え。舞の最中に、衣装のことを考えるんですか?」
「衣装をきれいに見せるためには、どう動いたらいいか、とか。このふりつけは、衣装のこの部分を見てほしい、とか。そういうことを考えていると、芽衣ならうまくいくかもしれないと思って」
衣装……、ああ、そっか。たしかに、そのほうが楽しそう。
わたしがつくる、きれいな衣装。その衣装を一番きれいに見せるための舞。
どうやったら、衣装を輝かせることができるのか――。
(ここの手の動きは、なめらかに。ふわっと手をあげるときは、そでを舞わせて)
思いだしながら、もう一度体を動かしてみる。
(うーんと、ここで、くるっと回る。あ。このとき、帯に長いりぼんをつけていたら、なびいてきれいに見えるかも?)
(つぎの動きは、こうして……、そのつぎは、こう!)
あれ、なんか、楽しくなってきたかも……!
つくりたい衣装が頭に浮かぶ。その衣装でどう舞うべきか、わかってくる。
ぱっと目の前が開けていく気分だよ!
「雷斗さま。すごいです! これならいけるかも!」
わたしは舞うのをやめて、勢いよくふり返った。
こっちを見ていた雷斗さまは、なぜかぽかんとしていたけど、すぐ我にかえって笑い出す。……え、なんで?
「芽衣、衣装のこと好きすぎるだろ」
「それはもちろん大好きですけど……、でも、なんで笑うんですか!」
「だって、急にうまく舞うようになったから」
「……わたし、うまくできてました?」
雷斗さまは笑いながら、こくっと、うなずいた。
「ああ。長年、舞を学んできた紅花どのと並ぶのは大変だろうけど、これなら、いい線いけると思う」
……そうだよね。
努力家の紅花さまに、超初心者のわたしが実力で追いつくのは、すごく難しいと思う。
でもだからこそ、できる努力を全部やらなきゃいけないんだ。
雷斗さまのおかげで、糸口はつかめたし。まだまだ、ここから。
「わたしはわたしの、衣装係としての舞を極めます!」
「ん。がんばれ。衣装も楽しみにしてる」
「はい! 儀式当日の紅花さまとわたしの衣装と、藍雪さまの衣装。それから、藍雪さまの婚礼の衣装もつくらなきゃ! あ、そうだ」
そういえば、わたし、雷斗さまに頼みたいことがあったんだ。
「また商人さんを紹介してもらえませんか? ほしいものがあって」
「ああ、いいよ。なにが必要なんだ?」
「糸です! 糸をたくさん!」
雷斗さまが不思議そうに首をかしげる。
「糸? 布じゃなくて?」
「はい。婚礼の衣装用の、白い糸をお願いします」
きっとすてきな衣装になるって予感がしてるんだ。楽しみにしててね!
それはそうと、つぎの日。
わたしの舞を見た紅花さまと侍女たちは、みんな目を丸めた。
「どうですか! 舞のこつ、つかめてきましたよ!」
侍女たちは紅花さまの様子をうかがうみたいに、そっと視線を送る。
紅花さまはうでを組んでそっぽを向きながら、ぼそっと言った。
「……まあ、悪くないわ。昨日の最悪な舞よりはね」
う、うん……? 一応ほめてくれてるっぽい? 喜んでいいのかな?
「でも、手の角度はこうよ」
突然、ずんずん近づいてきた紅花さまが、わたしの手を引っぱった。わ!
「はじまりから、手の角度も高さもちがうわ。いまのこの状態を覚えなさい」
「は、はい……!」
「指先に意識を向けて。つぎの足運びは、右足に重心を乗せると動きやすいわ」
てきぱき、てきぱき。紅花さまが鏡の前で、わたしに指示を出していく。
一気にまくしたてられて混乱するけど、鏡を見ているとわかる。
「さっきより、ずっときれいに舞えるようになってる……!」
「当然でしょ。わたしが教えているんだから」
つんとしてるけど、紅花さまの口もとは笑顔の形になってるみたい。
わたし、期待に応えられたかな? 衣装係としての舞、成功してる?
(よかった。ああ、こうなると、早く衣装をつくりたくなってくるね!)
うずうずする~! 待ち遠しいよ!

