


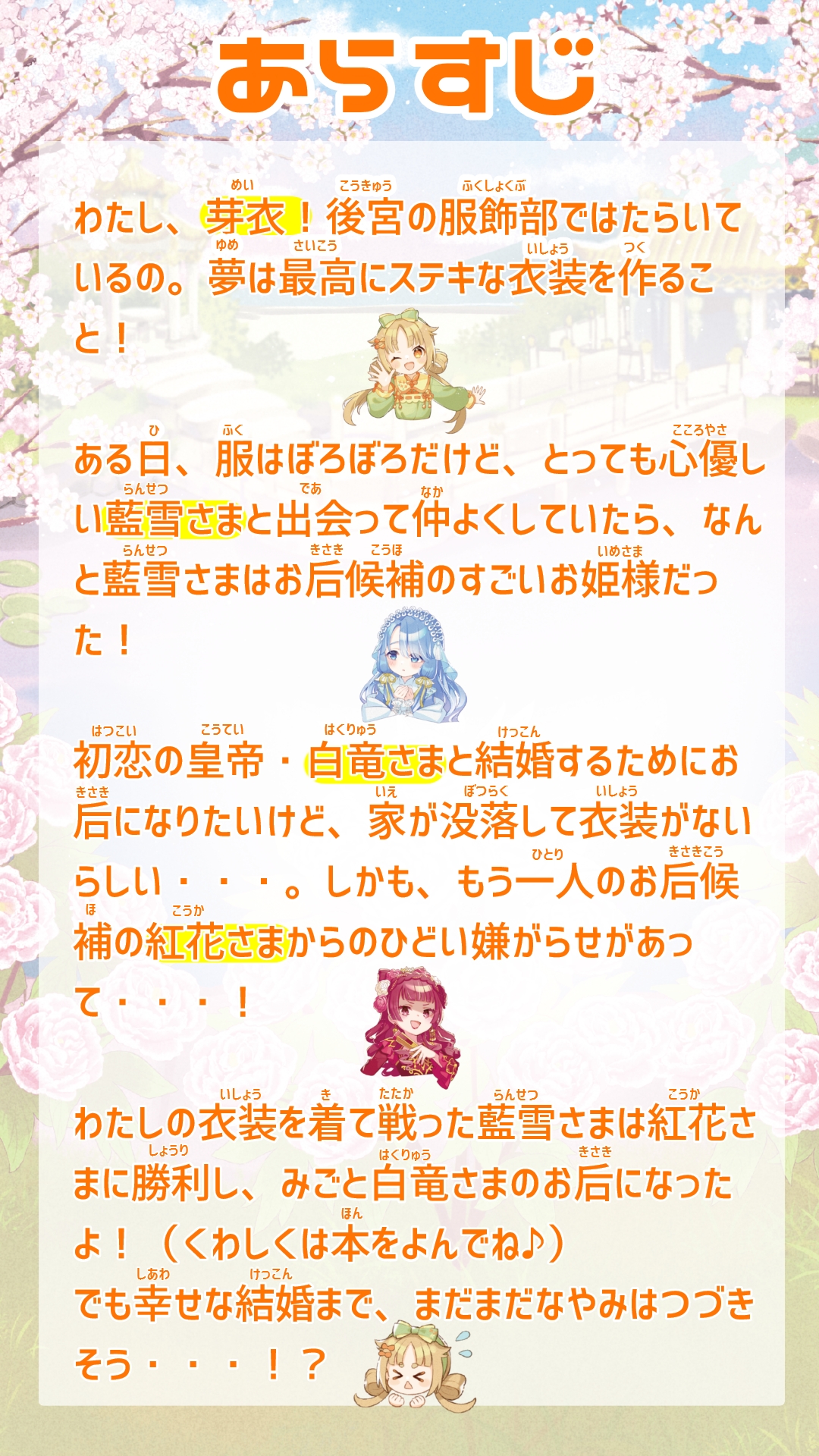


第4章
その日、わたしが天陽宮を出ようとすると、藍雪さまが声をかけてきた。
「芽衣、白竜さまの頼みごととはいえ、あなたも複雑でしょう。断ってもいいのよ。そのときは、わたしから白竜さまにお伝えするから」
眉を下げて心配そうな藍雪さまに、胸がじーんとする。
やっぱり藍雪さま、やさしいな。
「大丈夫ですよ。依頼を受けるかどうかはまだ決められないけど、とりあえず、いまから紅花さまの様子を見てきますね」
「そう……、無理はしないでね」
「はい。いってきます!」
藍雪さまにおじぎして、歩きだす。目指すは花殿――紅花さまの住む殿舎だ。
やっと着いた花殿は、天陽宮に負けないくらい大きな建物だった。
さて……、どうしようかな。
(『百命花の舞』で着る紅花さまの衣装をつくれ、って言われてもね)
それが白竜さまからの頼みごとだったんだ。でも……、ね。
もちろん、わたしは衣装づくりが大好きだよ。
だけど、紅花さまは后選びのときに競った相手なわけだし。
わたし、あの儀式以来、紅花さまに会ってないんだ。ちょっと気まずいっていうか、なんて声をかけたらいいかわからないっていうか――。
「あら、あなた」
「うわっ! ……あ、えっと、紅花さまの侍女さん?」
ふり返ると、いつのまにかひとりの侍女が立っていた。
(ま、まずい。心の準備がまだできてないよ! 冷や汗が!)
でもその侍女はすこし考える顔をしてから、わたしのうでを引いた。
「ちょっと来なさい」
「え、な、なんですか?」
「いいから、来るの。――ほら、見て」
ぐいぐいうでを引かれて連れていかれたのは、花殿の庭だった。
立ちどまった侍女が、建物の窓を指で示す。もう、本当になんなの……?
「あ。あれって、紅花さまですか?」
部屋には、扇を手にして舞っている紅花さまがいた。
つやのある赤い髪をなびかせて、紅花さまは真剣な顔で舞いつづける。
(うーん、相変わらずきれいなんだよなあ。やっぱり、藍雪さまが舞手にすすめるだけあるよ。……でも、なんだろう)
今日の紅花さま、すこし怖い気がする。
いつものいじわるな態度も怖いんだけど、それとはちょっとちがう。
鬼気迫るっていうのかな。そんな雰囲気が怖い。
「紅花さまは『百命花の舞』のために、ひとりでずっと練習しているのよ。だれも紅花さまに手をかそうとしないから」
侍女がくやしそうにくちびるをかんだ。
「いまの後宮では、藍雪さまが一番力を持ってる。だから因縁のある紅花さまを助けたら、藍雪さまを敵に回すんじゃないかって、みんなそう思って、紅花さまをさけてるの」
「え……。そうなんですか?」
「そうよ。舞を教えてくれるひともいない。全部、あなたたちのせい」
侍女がするどい目つきで、わたしをにらんだ。
……知らなかった。紅花さまがそんな状況になってるなんて。
(でも、わたしたちのせいって言われたって、困るよ)
紅花さまは休まずに舞の練習を繰りかえしている。
真剣に、必死に、何度も何度も――。
「儀式の衣装もつくれないの。うでのいい職人や宮女には、みんな断られたわ」
(……あ。もしかして)
白竜さまがわたしに衣装づくりを依頼したのは、そのせいなのかな?
后は、姫をまとめたり守ったりすることが仕事。後宮のなかで困っている姫がいたら、わたしたちはその子を助ける必要があるから――。
侍女が苦々しそうな顔でつぶやいた。
「あなたに頼むなんて嫌だけど、でも、背に腹は代えられないわ。……紅花さまの衣装をつくってくれない?」
と、そのとき、侍女がはっとして「紅花さま!」って叫んだ。
ばっと風を切って、彼女は窓辺にかけよっていく。
紅花さまが、舞の途中で足をもつれさせて転んじゃったみたいだった。
だ、大丈夫かな。結構派手に転んだみたいだけど……。
「紅花さま、もう何時間も練習されているんですから、すこし休みましょう?」
「――嫌よ!」
空気をさくみたいな紅花さまの声に、心臓がひゅっとする。
びっくりした……、というか、紅花さま、泣いてない?
「今度こそ成功させなきゃいけないの。もうお父さまにもお母さまにも恥をかかせるわけにはいかない。がっかりさせられないのよ……っ!」
紅花さまは泣きながら、侍女をにらみつけていた。それから、侍女が止めるのも聞かずに練習にもどっていく。見ているだけで、なんだか苦しくなった。
(こんな紅花さま、はじめて見たかも……)
いや、后選びに負けたときも、紅花さまは泣いていたっけ。
いじわるだけど責任感が強くて、まわりの期待に応えるために必死だったんだよね。
もしかしたら、后選びに負けた自分をたくさん責めたのかもしれない。
だから今度こそはって、こんなに練習をしているのかも……?
(でも、絶対無理してるじゃん。顔色悪いし。休んだ方がいいんじゃ)
そう思ったときだった。
「紅花さま⁉ だ、だれか来て……っ!」
あせった侍女の声がして、ざわざわと騒がしくなった。
って、あれ⁉ 紅花さま、倒れてる⁉
「紅花さま、紅花さま! ああ、どうしたら……」
集まってきた侍女たちが真っ青になって、おろおろと部屋の中を行ったり来たりする。
その侍女たちもみんな、やつれていた。
紅花さまにつきあって、侍女たちも休めてないのかも?
(みんな、頭が働いてないんだ。……あああ~、もう。仕方ないなあ!)
さすがに気まずいとか言ってられないよね!
「あのー! 帯をゆるめてあげてください!」
「え。あ、あなた、藍雪さまのところの……。なにしに来たのよ!」
さっき話していたのとはちがう侍女たちが、わたしをにらんでくる。
「わたしのことより、まずは帯!」
わたしは急いで部屋に入って、紅花さまの帯をゆるめた。
見るからに豪華な衣装は、きっちり帯を締めていて、きつそうなんだよね。
疲れているときにこんな衣装を着ていたら、具合だって悪くなるよ。
かわいい衣装は最高だけど、適材適所で使いわけるのも大切です!
「寝台に運びましょう。手伝ってください!」
侍女たちはすこし落ち着いたのか、気を失っている紅花さまを戸惑いながらも寝台に運んでくれた。
紅花さまが目を覚ましたのは、それからすこしして、日が暮れたころだった。
「どうして、あなたがここにいるのよ!」
……うーん、目が覚めたとたんに、にらまれました!
「えっと、たまたま通りかかりまして」
「どこをどう通りかかれば、あなたがわたしの寝室に来るっていうの!」
「それは……、いろいろです! くわしいことは気にしないでください!」
「するわよ!」
紅花さまは目をきっとつりあげて、肩でぜえはあと息をする。
ああほら、寝起きにそんな大声を出すからだよ。
でも、紅花さまは急に静かになって、視線を落とした。
「――わたしの衣装をつくれって、白竜さまに言われたのね」
え。な、なんでわかるの。
「ふんっ、図星ね。あなた、わたしには関わりたくないでしょう。こっちからしたって余計なお世話だし。帰ってちょうだい」
そう言って、肩にかかった赤い髪を手ではらう。
仕草はいつもどおりだ。でも、顔色が悪いせいで弱々しい感じがする……。
「衣装くらい、わたしひとりでなんとでもなるわ」
「……なんとかなってないじゃないですか。倒れてるし」
「うるさいわね! あなたには関係ないでしょう! ……なんとかするわよ。だれも助けてくれないんだから」
紅花さまが一瞬泣きそうな顔になって、部屋のすみに置かれた布地を見た。
あの布って、もしかして、自分で衣装をつくる気だったのかな?
お姫さまは裁縫も習っているはずだから、つくれないことはないだろうけど。
(でも、なんか嫌だよ。そんな顔で衣装をつくるなんて)
衣装や布や宝石には、もっときらきらした目を向けてほしい。
泣きそうな顔なんて見たくない。それに、無理もしてほしくない。
「とにかく、帰りなさい! いますぐに!」
強い口調の紅花さまは怖かった。だけど。
「――嫌です」
わたしの言葉に、紅花さまはぽかんとする。それから眉をひそめた。
「はあ? 嫌ってなに。わたしの命令が聞けないの?」
紅花さまの冷たい声が、頭につんと響く。
倒れてたくせに、あいかわらずの強気だ。
でも、嫌なものは嫌。そう思っちゃうんだから、仕方ないじゃん。
「わたしは藍雪さまの侍女で衣装係です。紅花さまの命令を聞く理由はありません。だから帰りません!」
「な、なによそれ。わたしは姫なのよ⁉」
「それがなんですか! だいたい、わたし、今日はずっと紅花さまの看病をしたんですけど⁉ 追いかえすなんてひどくないですか!」
「そ、れは……、看病してほしいなんて、頼んでないわ!」
紅花さまのつんつんした態度はゆらがない。
もーっ、いじわるお姫さまめ!
「さっさと帰りなさい!」
「だから、嫌ですってば! だって紅花さま――、泣きそうなんですもん!」
もう一度、ぽかんと紅花さまが口をつぐんだ。それから、目をそらす。
「……わたしが、泣くわけないでしょう」
「いいえ、泣きそうになっています。后選びのときもいまも、ずっと泣きそう、というか、さっき泣いてたじゃないですか」
わたしは、じっと紅花さまを見つめる。
「泣いてる子を放っておくほど、わたしは鬼じゃないんですよ」
きっと、藍雪さまも同じだと思うんだ。
后選びのとき、泣いている紅花さまに、手をのばそうとしたくらいだから。
だからわたしも、手をのばしたい。そう、だから――。
「紅花さま、わたしがあなたの衣装をつくります」
「え……?」
「紅花さまに似合う衣装を、必ず用意します。だから、つくらせてください」
まっすぐに紅花さまを見つめると、紅花さまは目を見開いた。
たっぷり間があく。それから、紅花さまは自分の額に手を当てた。
「なんなのよ。あなた、ばかじゃないの――」
また、沈黙。そのあと、紅花さまはぎゅっとこぶしをにぎった。
「……勝手にしなさいよ」

